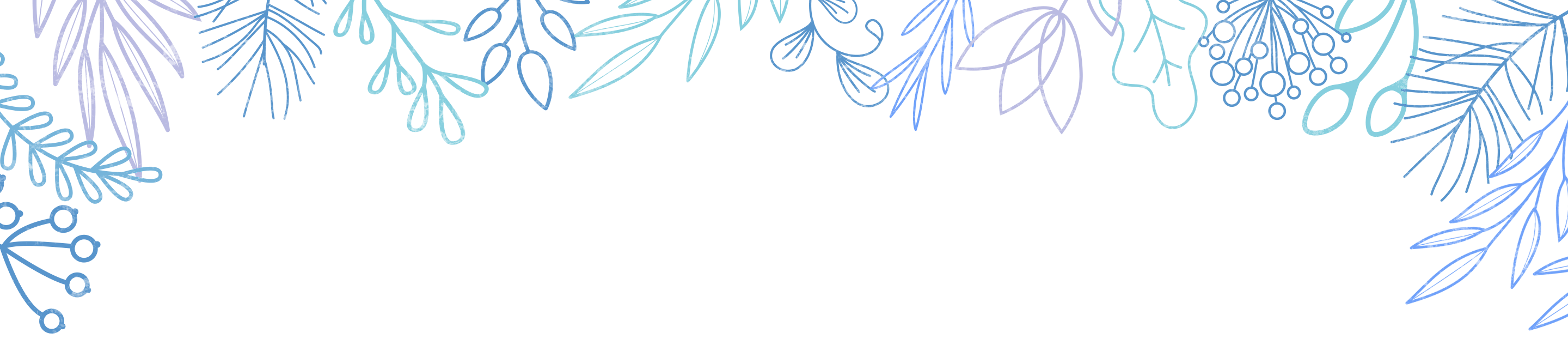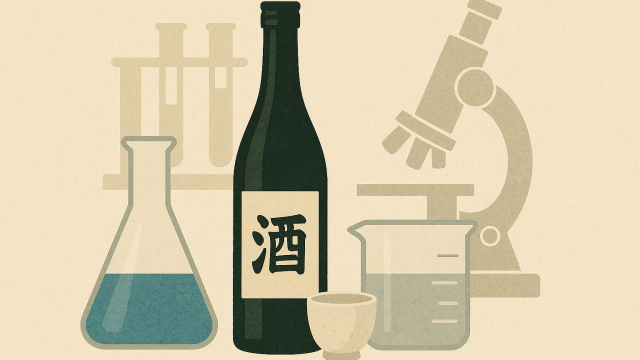北海道の新星:上川大雪酒造とその銘酒「上川」の全貌
1. はじめに:北海道の輝く新星 – 上川大雪酒造の物語
日本酒の世界において、北海道は近年、目覚ましい品質向上と個性的な酒造りで注目を集める産地となりつつある。その中でも、ひときわ異彩を放つ存在が上川大雪酒造である。2017年設立と比較的新しい酒蔵でありながら 、その名は瞬く間に全国の日本酒愛好家の間に広まった。その理由は、北海道最高峰・大雪山系の麓、上川町という清冽な自然環境に恵まれた立地 、そして「地方創生」という明確な使命感 にある。
上川大雪酒造は、単に高品質な日本酒を造るだけでなく、酒造りを通じて地域を活性化させることを目指している。その哲学は、主力銘柄である「上川」に凝縮されている。本稿では、この注目すべき酒蔵の設立背景から、酒造りの環境、哲学、製品ラインナップ、そして地域への貢献に至るまで、その全貌を詳細に解き明かしていく。
2. 構想から醸造へ:上川大雪酒造の誕生
上川大雪酒造の設立は、2016年から2017年にかけて具体化した 。特筆すべきはその設立経緯である。全国的に酒蔵数が減少する中、三重県にあった休眠中の酒造会社の酒類製造免許を北海道に移転するという、現代日本では異例とも言える手法を用いた 。これは、新規免許取得の困難さを示すと同時に、同社の革新的なアプローチを物語っている。北海道においては、戦後初の新規酒造会社設立であり 、その誕生は大きな注目を集めた。
緑丘蔵(りょっきゅうぐら):大雪山の恵みを受ける醸造所
上川大雪酒造の中核をなすのが、上川町に位置する「緑丘蔵」である。
- 所在地: 北海道上川郡上川町旭町25番地1
- 連絡先: TEL 01658-7-7388, FAX 01658-7-7377 (ギフトショップ:TEL 01658-7-7380 )
- 醸造開始: 2017年5月
大雪山系の麓という立地は、後述する良質な水と冷涼な気候という、酒造りにとってこの上ない恩恵をもたらしている。
「地方創生蔵」としての使命
上川大雪酒造は、自らを「地方創生蔵」と位置づけている 。人口約3,200人の上川町において 、酒造りを通じて雇用を創出し、近隣の層雲峡温泉 と連携した観光客誘致、そして地域ブランドの構築を目指している 。この挑戦は、単なるビジネスの枠を超え、地域社会の活性化に貢献しようという強い意志の表れである。その設立背景には、町民有志によるボランティアグループ「酒蔵支えTaI(さかぐらささえたい)」の存在など、地域コミュニティからの熱心な支援があったことも特筆すべき点である 。これは、酒蔵が設立当初から地域と共に歩む存在として計画されていたことを示唆している。酒蔵が地域経済や社会福祉の核となり、一般的な企業の目標を超える役割を担っているのである。
「飲まさる酒」:飲み手を魅了する哲学
上川大雪酒造が掲げる酒造りの核心的なコンセプトが「飲まさる酒」である 。これは「ついつい飲んでしまう」という意味の北海道弁であり、同社の目指す酒質を端的に表している。具体的には、料理の味を邪魔せず、むしろ引き立てるような綺麗でバランスの取れた味わい、すなわち究極の「食中酒(しょくちゅうしゅ)」を目指すことを意味する 。この哲学は、創業者である塚原敏夫氏のビジョン と、それを具現化する総杜氏・川端慎治氏の技術 によって支えられている。
3. 高地の醸造:水と気候という名の恵み
上川大雪酒造の酒質を決定づける重要な要素が、その類まれな自然環境である。特に、仕込み水と気候は、他の追随を許さない独自の個性を日本酒に与えている。
水源:大雪山系の恵み
酒造りの命とも言える仕込み水は、大雪山系の万年雪や湧水を源とする天然水である 。特筆すべきはその水温で、年間を通じて約7℃という低温を保っており、これは高品質な酒造りにとって理想的な条件と言える 。
水質:絹のような軟水
緑丘蔵で使用される水は、硬度約20mg/Lという「超軟水」に分類される 。一般的に軟水で仕込んだ日本酒は、口当たりが柔らかく、優しく繊細な酒質になる傾向がある 。上川大雪酒造の酒が持つ清らかさや滑らかさは、この超軟水の恩恵によるところが大きい。
しかし、単に「柔らかい」だけではないのが緑丘蔵の水の特異性である。通常、超軟水は口中で淡く、すぐに消え去るような印象を与えがちだが、緑丘蔵の水は「ある程度の量感というか芯のようなものを意識させながら、スルっと喉に滑っていく感じ」 と表現される。これは、硬度だけでは測れない、絶妙なミネラルバランスや水質の構造が、単なる軽さにとどまらない、綺麗でありながらも存在感のある酒質に寄与していることを示唆している。総杜氏の川端氏が「酒造りにおける水の大切さを改めて認識した」 と語るように、この水は上川大雪酒造の酒造りにおいて、まさに神様の贈り物と言える存在である。
気候:寒冷地というアドバンテージ
上川町の冷涼な気候(年間平均気温5.3~5.5℃ 、冬期は-20℃に達することも )も、酒造りに大きな利点をもたらしている。この寒さは、日本酒の吟醸香や綺麗な味わいを引き出す上で重要となる「低温長期発酵」を自然に促す 。また、醸造工程における温度管理を自然の力で助ける役割も果たしている 。
4. 醸造家の技:哲学、人、そして精密さ
上川大雪酒造の卓越した品質は、恵まれた自然環境に加え、明確な哲学、卓越した技術を持つ人材、そして細部にまでこだわる精密な作業によって支えられている。
北海道産米へのこだわり:地域のテロワール
同社は、原料米として北海道産米を100%使用することに徹底的にこだわっている 。主に使用されるのは、北海道が誇る3種類の酒造好適米である。
- 吟風(ぎんぷう): 北海道の酒米の先駆け的存在。米の中心にある白く不透明な部分「心白(しんぱく)」が大きく明瞭で、芳醇な香りと豊かな旨味、コクのある酒を生み出すとされる 。淡麗というよりは、しっかりとしたボディ感を持つタイプに仕上がることが多い 。特別純米酒などに用いられる 。
- 彗星(すいせい): 「初雫」と「吟風」の交配種。タンパク質含有量が低く、雑味の少ない綺麗な酒質に適している。大粒で収量性も高い。香りは穏やかで、味わいは淡麗辛口に仕上がる傾向がある 。純米吟醸酒などに用いられる 。
- きたしずく: 「吟風」のような大きな心白と、「彗星」のような収量性、耐冷性を併せ持つ新品種。雑味が少なく、柔らかくすっきりとした酒質が期待できる 。幅広い製品に使用されている 。
これら3つの個性豊かな道産米を戦略的に使い分けることで、上川大雪酒造は100%北海道産という原則を守りながらも、芳醇なタイプから淡麗なタイプ、そしてバランスの取れたタイプまで、多様なスタイルの日本酒を巧みに醸し分けている。これは、単に地元の原料を使うというだけでなく、それぞれの米が持つ特性を深く理解し、それを最大限に活かす技術力の高さを物語っている。
生産者との連携:種から酒へ
「顔のわかる生産者」との強い信頼関係も、同社の酒造りを支える重要な柱である 。特に隣町の愛別町 をはじめとする契約農家との密接な連携は、高品質な原料米の安定確保に不可欠である。総杜氏の川端氏は、誰がどこで米を作ったかを知ることの重要性を強調しており 、生産者との相互尊重に基づいた協力関係が、その酒造りの根幹をなしている 。
導く手:総杜氏・川端慎治
上川大雪酒造の酒造りを率いるのが、総杜氏の川端慎治氏である 。石川県、福岡県、岩手県、山形県、群馬県など、全国5県の酒蔵で経験を積んだ後 、北海道へ帰郷。以前在籍した金滴酒造では、道産米「吟風」100%の酒で全国新酒鑑評会金賞を受賞するという、北海道の酒造史に残る快挙を成し遂げた 。上川大雪酒造の設立当初から杜氏として参画し 、その卓越した技術と「飲まさる酒」を追求する哲学 は、同社のアイデンティティそのものである。現在は、姉妹蔵である碧雲蔵(帯広市)、五稜乃蔵(函館市)の酒造りも統括し、さらに帯広畜産大学の客員教授として後進の指導にもあたっている 。
緻密な手法:小仕込み、大いなる手間
「丁寧な小仕込み」 は、上川大雪酒造の品質を支える醸造スタイルである。仕込みタンクは全て2500リットル未満、1タンクあたりの米の使用量は600~750kgに抑えられている 。洗米は10kgずつ時間を計って吸水させ、放冷機は使わず手作業による自然放冷、麹造りは6~7kg盛りの小さな麹箱で行うなど、非常に手間のかかる工程を採用している 。驚くべきは、この大吟醸造りに匹敵するレベルの丁寧な作業が、精米歩合70%の純米酒から35%の純米大吟醸まで、全ての製品に適用されている点である 。これは、単なる「小仕込み」という言葉以上に、品質に対する妥協のない姿勢を示すものであり、同社の酒が高く評価される所以であろう。伝統的な手造りの技と、最新の設備・品質管理体制が融合し 、安定した高品質を実現している。
5. 「上川」を味わう:シグネチャーブランドの探求
上川大雪酒造を代表するブランドが「上川」である。この銘柄は、同社の哲学と技術が結晶した、まさに顔と言うべき存在だ。ラインナップの中心は、特別純米、純米吟醸、純米大吟醸であり 、全てが米と米麹、水のみで造られる純米タイプであることは、同社の理念を反映している 。
「上川」ブランド スペック一覧
以下の表は、「上川」ブランドの主要製品について、現在入手可能なスペック情報をまとめたものである。ただし、公式に全てのスペックが公開されているわけではない点に留意が必要である。
| 製品名 | 使用米 | 精米歩合 | アルコール度数 | 日本酒度 | 酸度 | 価格 (720ml, 税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川大雪 特別純米 吟風辛口 | 吟風 (愛別町産) | 60% | 16度 | +6 (非公開) | 非公開 | 2,530円 |
| 上川大雪 純米吟醸 彗星 | 彗星 | 50% | 16度 | 非公開 | 非公開 | 2,970円 |
| 上川大雪 純米大吟醸 彗星 | 彗星 | 35% | 16度 | 非公開 | 非公開 | 4,070円 |
| 上川大雪 特別純米 きたしずく | きたしずく | 60% | 16度 | 非公開 | 非公開 | 2,200円 |
(注:日本酒度、酸度については非公開の場合が多い。価格は参考情報。)
この表は、限られたデータではあるが、製品間の比較を可能にする。例えば、特別純米と純米吟醸・大吟醸では精米歩合が異なり、それが味わいの方向性に影響を与えていることが推察される。
感覚的特徴:「上川」の味わい
様々なレビューや説明から浮かび上がる「上川」ブランドの味わいの特徴は、以下のキーワードに集約される 。
- 香り: 穏やかで、綺麗。主張しすぎず、時にマスカット や穀物 のようなニュアンスを感じさせる。
- 味わい: 最大の特徴は「綺麗さ」と「バランス」。滑らかな口当たりで、米由来の旨味はしっかりと感じられるものの、洗練されている。酸味が味わいに骨格を与え、フレッシュさを演出している 。
- 後味: キレが良く 、爽やか。食中酒としての適性の高さを物語っている。
- 総合印象: 「飲まさる酒」のコンセプト通り、非常に飲みやすく、料理との相性が良い。大雪山系の水と北海道産米の質の高さを素直に表現した、丁寧な造りを感じさせる酒質である。
楽しみ方:北海道の恵みと共に
「上川」ブランドの酒は、その綺麗でバランスの取れた味わいから、冷酒から常温で楽しむのが最適とされることが多い 。ペアリングとしては、やはり北海道の豊かな食材が推奨される。新鮮な魚介類はもちろん、乳製品、野菜、さらには淡白な肉料理など、素材の味を活かした料理と合わせることで、酒と料理双方の魅力が一層引き立つだろう。
6. さらなる探求:季節の酒と限定品
上川大雪酒造は、定番の「上川」ブランドに加え、季節感や特別なコンセプトを反映した多様な限定酒も醸造しており、日本酒愛好家の探求心をくすぐる。
季節の彩り:限定酒
北海道の四季を映し出すかのように、季節ごとに限定酒が登場する。春にはフレッシュな新酒、夏には爽快な夏酒、秋には円熟味を増したひやおろし、冬にはしぼりたての生酒やにごり酒などが期待される 。
特別な一本:限定リリース
これまでにリリースされた限定品や特別品には、以下のようなものがある。
- 「辛口 生」: キレの良い辛口の生酒 。
- 「雫取り」: もろみを袋吊りし、自然落下する雫だけを集めた最高級品 。
- 「氷晶にごり」: 冬の情景を思わせるにごり酒 。
- コラボレーション酒: 地元のホテル や百貨店 など、他業種との連携によるユニークなボトルも存在する。
蔵元限定の魅力
緑丘蔵のギフトショップや特定の地域でのみ販売される限定品も存在する。地域限定銘柄「神川(かみかわ)」 や、ギフトショップ限定の「雫取り」 などは、現地を訪れる大きな動機となるだろう 。
これらの多様な限定品の存在は、定番ブランドの安定した品質に加え、常に新しい挑戦を続ける同社の姿勢を示している。また、限定品は希少性から収集家の関心を引き、蔵元への訪問や直接購入を促す戦略的な側面も持っている。
7. 源流を訪ねて:緑丘蔵での体験
上川大雪酒造の酒造りの現場である緑丘蔵では、訪問者がその雰囲気に触れる機会が設けられている。
酒蔵見学
衛生管理上の理由から、蔵内部への立ち入りは通常許可されていない 。しかし、建物の外に設けられた見学窓から、ガラス越しに醸造工程の一部(タンクなど)を見学することが可能である 。予約は不要で自由に見学できるが 、冬期間は積雪により窓からの見学が困難になる場合がある点に注意が必要だ 。醸造は主に10月から翌年7月にかけて行われる 。
日本酒テイスティング
試飲については、情報が錯綜している。無料試飲が可能とする情報 、有料試飲があるとする情報 、試飲自体が中止されている可能性を示唆する情報 が存在する。訪問前に最新の状況を確認することが推奨される。試飲が可能な場合、定番銘柄や限定酒が提供される可能性がある 。運転者や未成年者への試飲提供は不可である。
ギフトショップ(緑丘蔵 Gift Shop)
- 場所: 酒蔵に隣接 。北海道上川郡上川町旭町25番地1 。
- 営業時間: 夏季 10:00~16:00、冬季 10:00~15:00 。
- 定休日: 不定休。訪問前に問い合わせるのが確実 。
- 取扱商品: 定番の「上川」ブランド、蔵元限定酒(「神川」、「雫取り」 など)、酒粕を使用した食品(ラーメン 、プリン など)、酒器や手ぬぐいといったオリジナルグッズも販売されている 。
- 連絡先: TEL 01658-7-7380 。
8. 高まる評価と広がるネットワーク:名声と姉妹蔵
設立からわずかな期間で、上川大雪酒造はその品質と独自の哲学で高い評価を獲得し、着実にそのネットワークを広げている。
市場の評価と評判
新しい酒蔵でありながら、その名は急速に広まり、日本酒愛好家からの注目度は高い 。特に総杜氏・川端慎治氏への期待は大きく、「カリスマ杜氏」としての評価も、その評判を後押ししている 。レビューからは、品質の高さ、安定感、そして「飲まさる酒」としての個性が一貫して評価されていることがうかがえる 。
受賞歴と認定
その実力は数々の受賞歴にも表れている。
- 札幌国税局新酒鑑評会: 道産米吟醸酒の部、純米酒の部などで金賞を複数回受賞 。
- 北海道米でつくる日本酒アワード: 各部門で受賞 。
- JAL国内線ファーストクラス採用: 「上川大雪」ブランドの酒が複数回採用されている 。
- Makuakeクラウドファンディング: 設立時の資金調達に成功 。
- 松尾大社 酒-1グランプリ: 参加実績あり 。
これらの受賞歴は、同社の酒造技術の高さと品質の安定性を示す客観的な証左と言える。
酒蔵ネットワーク:姉妹蔵の展開
上川大雪酒造は、緑丘蔵を核としながら、北海道内の他の地域にも拠点を設け、それぞれが地域の特性を活かした酒造りを行うというユニークな戦略を展開している。
- 碧雲蔵(へきうんぐら)、帯広市: 日本で唯一、国立大学(帯広畜産大学)のキャンパス内に設立された酒蔵 。十勝地方の資源を活用し、大学との共同研究や人材育成にも力を入れている 。主力銘柄は「十勝」。緑丘蔵よりも硬度の高い水を使用している 。
- 五稜乃蔵(ごりょうのくら)、函館市: 2021年、廃校となった小学校跡地に設立 。函館市にとっては54年ぶりとなる酒蔵の復活であり、地域からの期待も大きい 。主力銘柄は「五稜」。函館弁で「ついつい飲んでしまう」を意味する「はかいく酒」を目指している 。函館工業高等専門学校と連携し 、仕込み水には松倉川水系の超軟水を使用 。2024年10月には「函館五稜乃蔵株式会社」として独立した 。
- 網走酒蔵(計画中): 2026年開設予定。産学官連携をテーマとする 。
この多拠点展開は、単なる規模拡大ではない。それぞれの土地の水や米、そして大学や地域社会との連携といった「場所性」を重視した酒造りを、北海道の異なる地域で実践する試みである。これは、「地方創生蔵」というコンセプトを上川町だけでなく、道内各地へと広げる戦略的な動きであり、同社の独自性を際立たせている。
9. 結論:上川大雪酒造のエッセンス
上川大雪酒造は、設立からわずかな期間で日本の日本酒シーンに確固たる地位を築きつつある、注目すべき存在である。その成功の要因は多岐にわたるが、以下の点が特に重要である。
- 新しさと実績の両立: 若い酒蔵でありながら、数々の受賞歴や高い評価が示すように、確かな品質を実現している。
- 北海道への深いコミットメント: 大雪山系の清冽な水、吟風・彗星・きたしずくといった道産米、そして地域の人々との連携を酒造りの根幹に据えている。
- 卓越した醸造技術: 川端慎治総杜氏率いる醸造チームの経験と技術、そして小仕込みによる丁寧な手仕事が、その品質を支えている。
- 「飲まさる酒」という哲学: 料理を引き立て、飲み飽きしない、綺麗でバランスの取れた食中酒を目指す明確なビジョン。
- 地域活性化への貢献: 酒造りを核とした多角的な地域貢献活動と、道内複数拠点での展開による地方創生モデルの実践。
主力銘柄である「上川」は、これらの要素を結晶させた、まさに同社の顔である。清らかさ、バランスの良さ、そして北海道のテロワールを感じさせる表現力、料理との相性の良さがその特徴と言えるだろう。
今後の上川大雪酒造は、品質へのこだわりを維持しながら、網走での新蔵計画など、さらなる革新と挑戦を続けることが予想される。その動向は、日本国内のみならず、海外からも注目を集めるだろう。そして、同社の存在は、北海道が良質な日本酒産地として、その評価をさらに高めていく上で、重要な役割を果たしていくに違いない。