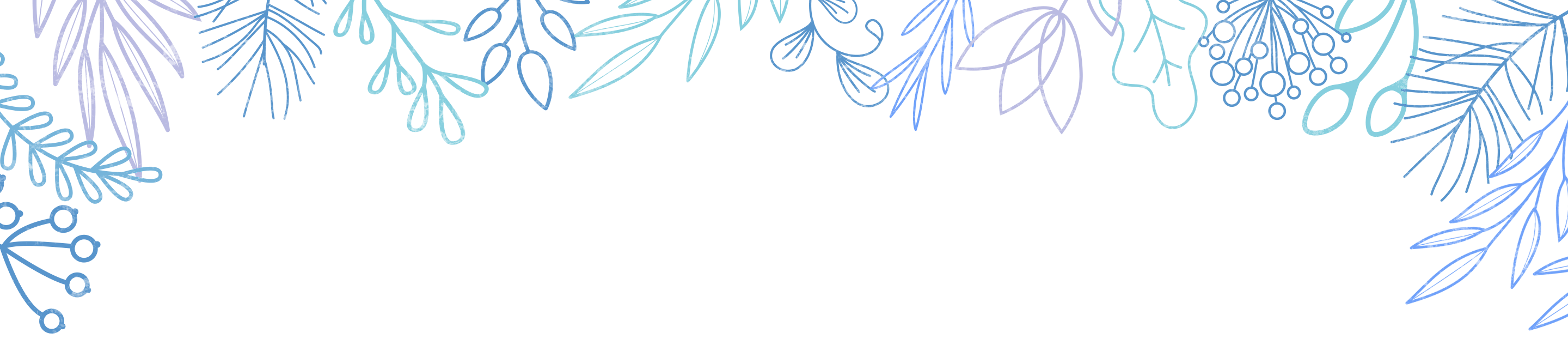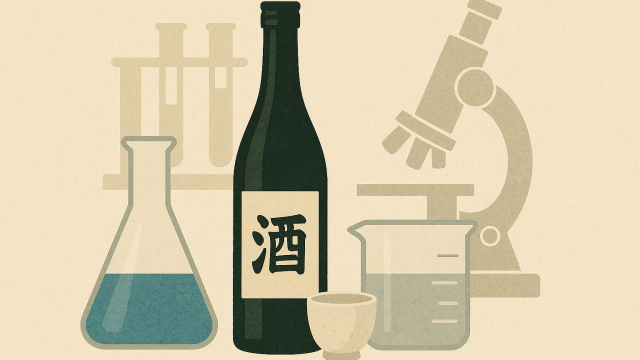福司:釧路の魂、北の大地に咲く百年酒
序章:福司 – 釧路の風土が醸す、不屈の魂
広大な釧路湿原、ドラマチックな海岸線、そして手つかずの自然が息づく街、北海道・釧路。この独特な風景の中に、100年以上にわたり地域の酒文化を守り続ける孤高の灯台のような存在があります。それが、釧路地方唯一の酒蔵、福司酒造株式会社です。
その名は「福司(ふくつかさ)」。
「福を司る」、すなわち「飲む人に福を招き、幸せを呼ぶ酒でありたい」という願いが込められています。この名前は単なる商標ではなく、地域社会に深く根ざし、その生産量の大部分が地元で愛飲されるという、まさに「地酒」としての哲学を体現しています。福司酒造の存在は、単なる酒造メーカーにとどまらず、釧路という土地の個性、厳しさ、そして豊かさを映し出す鏡のようなものです。その酒造りは、釧路の自然環境と分かちがたく結びついており、醸される一滴一滴が、この地の風土と人々の暮らしに寄り添ってきた証と言えるでしょう。
この記事では、福司酒造の驚くべき歴史、北海道の自然の恵みを最大限に活かす醸造哲学、多彩な酒のラインナップ、そして釧路コミュニティとの揺るぎない絆を辿る旅へと読者を誘います。
百年の軌跡:一度も止まることのなかった酒造り
福司酒造の物語は、大正8年(1919年)、初代・梁瀬長太郎氏が釧路市米町に酒類、清涼飲料、食品などの卸売業「合名会社敷島商会」を創業したことから始まります。転機が訪れたのはその3年後、大正11年(1922年)。現在の所在地である釧路市住吉に酒造蔵を新築し、日本酒「福司」の醸造を開始しました。
特筆すべきは、「福司」という銘柄の由来です。これは、当時取引のあった新潟県長岡の酒蔵(関原酒造)が製造していた銘柄でした。その蔵元から「釧路は水が美味しく、冷涼な気候は酒造りに向いている」と勧められ、その可能性を信じて銘柄を譲り受けたのです。これは、福司酒造が創業初期から確立された酒造りの伝統と品質基準を意識していたことを示唆しています。単に新しい事業を始めるのではなく、既存の評価ある銘柄を引き継ぐことで、品質へのコミットメントと、広域な酒造りの文脈の中での自社の位置づけを明確にしたと言えるでしょう。
そして、福司酒造の歴史を語る上で欠かせないのが、太平洋戦争下という未曽有の国難においても、一度も酒造りを休止しなかったという事実です。国策による企業統廃合や深刻な原料米不足により、全国の多くの酒蔵が休業や廃業を余儀なくされる中、福司酒造は醸造を継続しました。これは全国的に見ても極めて稀なケースであり、その具体的な理由は資料には明記されていませんが、並外れた経営努力、地域社会からの強い支持、そして釧路における不可欠な存在としての認識があったことを強く示唆しています。厳しい状況下で必要不可欠な資源(米、燃料、労働力)を確保し、統廃合を免れた背景には、単なる幸運以上の、地域に深く根ざした存在であるが故の強靭さがあったと考えられます。この「途切れることのない歴史」は、福司酒造の揺るぎないアイデンティティの中核を成しています。
戦後も福司酒造は歩みを止めませんでした。昭和40年(1965年)には卸売部門を株式会社敷島商会として分離独立させ、昭和32年(1957年)にはオートメーション化された工場を整備して大量消費時代に対応。そして昭和46年(1971年)には、当時流通の難しさや品質管理の問題から商品化が稀であった「生酒」を道内で初めて販売し、大ヒットさせました。これは、伝統を守りつつも革新を恐れない姿勢の表れです。平成3年(1991年)には社名を福司酒造株式会社へと変更し、梁瀬誠也氏が代表取締役に就任。その後、平成15年(2003年)には梁瀬之弘氏が代表取締役に就任し、平成22年(2010年)にはリキュール製造免許を取得するなど、時代の変化に対応しながら発展を続けています。
福司酒造 歴史的マイルストーン
| 年代 | 主な出来事 | 意義 |
|---|---|---|
| 大正8年 (1919) | 初代 梁瀬長太郎が合名会社敷島商会を創業 | 酒類・食品卸売業としてスタート |
| 大正11/12年 (1922/23) | 現所在地に酒蔵を新築、「福司」の醸造を開始 | 新潟の蔵元から銘柄を継承し、釧路での酒造りを本格化 |
| 太平洋戦争中 | 一度も休造せず醸造を継続 | 全国的に稀有な事例、地域との強い絆と不屈の精神を示す |
| 昭和46年 (1971) | 道内で初めて生酒を販売 | 流通が困難な中での挑戦、ヒット商品となり現在も人気 |
| 平成3年 (1991) | 福司酒造株式会社として発足、梁瀬誠也氏が社長就任 | 会社組織と社名を変更 |
| 平成15年 (2003) | 梁瀬之弘氏が代表取締役就任 | 現体制へ |
| 平成22年 (2010) | リキュール製造免許取得 | 商品ラインナップの多様化へ |
| 近年 | 全量道産米への移行、新ブランド「五色彩雲」発表 | 地域資源へのコミットメント強化、未来への挑戦 |
北海道の恵みを醸す:福司のテロワール
福司酒造の酒造りは、釧路の、そして北海道の自然環境と深く結びついています。それは単なるマーケティング上の謳い文句ではなく、酒質を決定づける根本的な要素であり、福司の酒を唯一無二の存在たらしめている源泉です。
釧路の気候というアドバンテージ
釧路の気候は、日本酒造りにとって特異な、そして非常に有利な条件を備えています。年間を通じて冷涼で、特に夏場は寒流である親潮の影響で気温が上がりにくく、安定した低温環境が保たれます。これは、日本酒の品質を左右する「熟成」と「貯蔵」に最適な条件です。一方、冬。外気温はマイナス10℃を下回ることもありますが、歴史ある土壁の蔵内は不思議と5℃前後を保ちます。この自然の恵みとも言える安定した低温環境が、10月下旬から4月下旬にかけて行われる「寒仕込み」(かんじこみ)において、酵母の活動を穏やかにし、きめ細やかで雑味の少ない酒質を生み出す長期低温発酵を可能にしているのです。蔵では、気温が低い時期には蒸米を二階に運んで自然放冷したり、タンクに冷却用と保温用のジャケットを使い分けたりと、気候を最大限に活かす工夫が凝らされています。
命の水:釧路湿原が磨いた伏流水
日本酒の約8割を占める「水」。福司酒造が使用する仕込み水は、まさにこの土地ならではの宝です。水源は、阿寒摩周国立公園内の摩周湖や屈斜路湖に端を発し、広大な釧路湿原をゆっくりと流れる釧路川水系の伏流水(ふくりゅうすい)。火山性地質や、植物が堆積してできた泥炭層(ピート層)を多く含む湿原の大地を時間をかけて浸透する中で、自然に濾過され、磨かれた清冽な水です。この水は、酒蔵近くの専用井戸から汲み上げられています。具体的な水質データは限られますが、北海道の水質や、醸される酒の「淡麗」さ、「やわらかさ」といった特徴から、ミネラル分が比較的少ない「軟水」または「中硬水」に近い性質を持つと推測されます。軟水は、発酵が穏やかに進み、口当たりが柔らかく、きめ細やかな酒質を生む傾向があります。まさに「この水なくして福司なし」と言われる所以です。
北海道産米へのこだわり
福司酒造は、近年、使用する米をすべて北海道産米に切り替えました。これは、地域への強いコミットメントの表れであり、北海道のテロワールを追求する姿勢を示しています。主に使われるのは、北海道で開発された酒造好適米(酒造りに適した米)です。
- 吟風(ぎんぷう): 2000年に誕生した北海道産酒造好適米の先駆け。米の中心にある「心白(しんぱく)」という白く不透明な部分の発現が良く、これが大きいと麹菌が繁殖しやすく、芳醇な香りと味わい深い酒になりやすいとされます。福司の純米酒などに使われ、しっかりとした米の旨味を引き出すのに貢献しています。
- 彗星(すいせい): 2006年登場。タンパク質の含有量が低く、大粒であることが特徴。タンパク質は雑味の原因となるため、これが少ないと、すっきりとキレの良い、いわゆる「淡麗」な酒質になりやすいと言われます。福司の純米吟醸酒や海底力 大吟醸などに使用され、その軽快な飲み口に寄与しています。
- きたしずく: 2014年登場の比較的新しい品種。「吟風」のような心白の大きさと、「彗星」のような収量性の高さを併せ持ちます。雑味が少なく、柔らかですっきりとした酒質が期待されるとされ、福司では大吟醸クラスの限定品などに用いられています。
手造りの技と若い力
福司酒造の酒造りは、伝統的な「手造り(てづくり)」の工程を大切に守り続けています。例えば、蒸米を作るための「甑(こしき)」は大型で、蒸し上がった米を取り出す際には、蔵人が中に入ってスコップで作業する必要があります。また、麹(こうじ)造りには、道南産の杉材で作られた特注の木製の麹箱を使用するなど、道具にもこだわりが見られます。一方で、醪(もろみ)を搾る工程では自動圧搾機を導入するなど、必要な部分では近代的な技術も取り入れています。
しかし、手造りの工程が多いということは、それだけ杜氏(とうじ)や蔵人(くらびと)の経験と勘、そして科学的根拠に基づいた確かな技術が不可欠であることを意味します。福司酒造の特徴的な点は、その蔵人チームが道内でも屈指の若手揃いであることです。彼らは、長い歴史の中で培われた伝統技術を受け継ぎながらも、新しい知識や感性を持ち込み、近年の品質向上や革新的な商品開発に貢献していると考えられます。伝統的な手法と若いエネルギーの融合が、福司酒造の今を支え、未来を切り拓く原動力となっているのです。
福司を味わう:北の大地の風味パレット
福司酒造が醸す酒は、釧路の風土と食文化に深く根ざした味わいを持ちます。その中心となるのが、社名と同じ名を冠した「福司」ブランドです。
フラッグシップ「福司」の哲学
「福司」ブランドの酒は、総じてバランスが良く、飲み飽きしない食中酒として設計されています。派手さはないものの、日々の晩酌(ばんしゃく)に寄り添い、特に北海道、釧路の豊かな食材、とりわけ新鮮な魚介類との相性を重視して造られています。多くのレビューで「淡麗(たんれい)」つまり軽快でスムーズな飲み口と評されつつも、米本来の旨味(うまみ)もしっかりと感じられるのが特徴です。
定番の味わい:コアラインナップ
- 福司 純米酒: 主に北海道産酒造好適米「吟風」を使用。吟風の特徴である芳醇さを活かし、米の旨味とふくよかな味わいが感じられますが、後味はすっきりとキレが良いのが特徴です。冷やしても、常温でも、燗にしても楽しめる万能タイプです。代表的なスペックは、アルコール度数14%、日本酒度+4.0(やや辛口)、酸度1.5、精米歩合60%です。
- 福司 純米吟醸酒: 主に北海道産酒造好適米「彗星」を使用しています。彗星由来のすっきり感に加え、福司らしい優しい甘さと酸味、そして食事の邪魔をしない穏やかな吟醸香(ぎんじょうか)が特徴です。なめらかな口当たりで、冷酒から常温でその香りと味わいを楽しむのがおすすめです。代表的なスペックは、アルコール度数15%、日本酒度+3.0、酸度1.5、精米歩合60%です。
- 福司 大吟醸酒: 蔵の技術の粋を集めた最高峰クラス。全国新酒鑑評会などで数々の受賞歴を誇ります。洗練された香りと、複雑で深みのある味わいが期待されます。毎年11月に釧路地域限定で発売される木箱入りの「霧笛(むてき)」など、特別な限定品も存在します。
個性が光る:ユニーク&イノベーティブな酒
定番に加え、福司酒造は独創的なアプローチから生まれた個性的な酒も造っています。これらは、伝統的なラインナップを補完し、新しい味わいを求める層や、特別な体験を求めるファンに応えるものです。
- 海底力(そこぢから): 釧路コールマイン株式会社が所有する太平洋海底炭鉱の坑道で、約1年間貯蔵・熟成させた大吟醸酒。原料米には「彗星」や「きたしずく」を使用。年間を通じて温度変化が少なく、紫外線が一切当たらない海底坑道というユニークな環境が、酒質を柔らかく、まろやかに変化させます。穏やかな熟成香と芳醇な飲み口が特徴で、やや辛口とされています。その希少性から入手困難な銘柄の一つです。
- 花華(はなはな): 北海道で初めて、自生する「はまなす」(日本の野生バラの一種)の花から分離された独自の酵母を使用して醸した純米酒。通常の清酒酵母とは異なる独特の酸味と味わいが特徴で、軽やかで華やかな印象を与え、日本酒初心者や女性にもアピールする可能性があります。
- YONAGA(よなが): 「夜長」の名が示す通り、ゆっくりと時間をかけて味わうことをコンセプトにした吟醸酒。若々しい華やかさよりも、熟成による落ち着いた味わいと穏やかな香りを重視しています。食中酒としても適しており、冷酒から常温がおすすめです。原料米は「吟風」、精米歩合60%、アルコール度数15%、日本酒度+4、酸度1.5です。
- COCOROMI(こころみ): 通常、日本酒造りには黄麹菌が使われますが、この純米酒は焼酎などに使われる「白麹菌」を用いて試験醸造された意欲作。白麹はクエン酸を多く生成するため、柑橘類を思わせる爽やかな酸味が特徴となります。この酸味がシーフード料理など、現代の食生活によく合うと考えられています。
- 太陽色のひととき(たいよういろのひととき): 同じく白麹を使用したスパークリング清酒。白麹由来のしっかりとした酸味と、瓶内二次発酵(シャンパンと同様の製法)によるきめ細やかな泡立ちが特徴。甘さを抑えたドライな味わいを目指し、シャンパンやカヴァのように、様々な料理とのペアリングが楽しめる新しいタイプの日本酒として開発されました。
季節の便り:限定酒の魅力
福司酒造は、季節ごとに限定酒をリリースし、多くのファンを魅了しています。これらの限定品は、その時期ならではの味わいを提供し、蔵と消費者との繋がりを深める役割も果たしています。
- 活性清酒 純生(かっせいせいしゅ じゅんなま): 毎年12月上旬に発売される季節限定酒。搾る前の醪(もろみ)を粗く濾し、加熱処理(火入れ)を一切行わずに瓶詰めした、生の濁り酒(にごりざけ)です。瓶内で酵母が生きているため、炭酸ガスが発生し、開栓時には吹き出すことがあるため注意が必要です。シュワシュワとした爽快な口当たりと、フレッシュな味わいが特徴です。
- しぼりたて生酒(しぼりたてなまざけ): 毎年1月下旬に発売される新米新酒。その年の新米で仕込み、搾ったばかりの酒を濾過せず(無濾過)、加熱処理せず(生酒)そのまま瓶詰めします。若々しくフレッシュな味わい、麹由来の自然な甘みが特徴で、新酒ならではの活き活きとした生命力を感じさせます。
その他の楽しみ方
上記のほかにも、福司酒造では日常的に楽しめる本醸造酒や普通酒(「本稀(ほんき)」など)、酒粕や甘酒、さらには日本酒を使った「地酒ケーキ」(金:吟醸酒使用、銀:純米酒使用)など、多彩な商品を展開しています。可愛らしいクマやタンチョウを模した陶器入りの商品は、北海道土産としても人気があります。これらの商品は、蔵元直売所やオンラインショップで購入可能です。
福司酒造 代表的な日本酒ポートフォリオ
| 銘柄名 | タイプ | 主要原料米 | 主なスペック (度数, 日本酒度, 酸度, 精米歩合) | 特徴・味わい | おすすめ温度帯 (情報あれば) |
|---|---|---|---|---|---|
| 福司 純米酒 | 純米酒 | 吟風 | 14%, +4.0, 1.5, 60% | 米の旨味、ふくよかさ、後味すっきり。バランスが良い食中酒 | 冷~燗 |
| 福司 純米吟醸酒 | 純米吟醸酒 | 彗星 | 15%, +3.0, 1.5, 60% | 優しい甘味と酸味、穏やかな吟醸香、なめらか | 冷~常温 |
| 福司 大吟醸酒 | 大吟醸酒 | (各種) | (非公開多) | 蔵の最高峰。洗練された香りと味わい。霧笛など限定品あり | (一般的に冷酒) |
| 海底力 (そこぢから) | 大吟醸酒 | 彗星/きたしずく | 15-16%, +0.5, 1.4, 55% | 海底熟成によるまろやかさ、穏やかな熟成香、やや辛口 | (一般的に冷酒) |
| 花華 (はなはな) | 純米酒 | (非公開) | 14% | はまなす花酵母使用。独特の酸味と味わい | (情報なし) |
| YONAGA (よなが) | 吟醸酒 | 吟風 | 15%, +4, 1.5, 60% | 落ち着いた味わいと熟れた香り。ゆっくり楽しむ食中酒 | 冷酒~常温 |
| COCOROMI (こころみ) | 純米酒 | (非公開) | (非公開) | 白麹使用。クエン酸由来の爽やかな酸味 | (情報なし、冷酒推奨か) |
| 太陽色のひととき | スパークリング | (非公開) | (非公開) | 白麹使用。しっかりした酸味ときめ細かい泡。ドライ | 冷酒 |
| 活性清酒 純生 | (にごり生) | (非公開) | (非公開) | 12月限定。酵母が生きている発泡性にごり酒。フレッシュ | 冷酒 |
| しぼりたて生酒 | (無濾過生) | (非公開) | (非公開) | 1月限定。新米新酒のフレッシュさ、若々しい甘み | 冷酒 |
単なる酒にあらず:福司と釧路コミュニティ
福司酒造は、単に釧路にある酒蔵というだけでなく、地域社会に深く根ざした存在です。その証拠に、生産される日本酒の約8割が地元である釧路管内で消費されています。この驚異的な地元消費率は、単なる市場の数字ではなく、福司の酒が地域の人々の生活の一部となり、文化として深く浸透していることを物語っています。この強い地域との絆は、おそらく同社が戦時下という困難な時代を乗り越えられた要因の一つでもあるでしょう。
地域の食との共生
福司酒造は、その酒造りにおいて、釧路をはじめとする北海道の豊かな食、特に豊富な海産物との相性を常に意識しています。レビューを見ても、「海鮮には欠かせない」、「北海道の食材によく合う」、「鯖&鮫をお供に楽しんでましたが、やはり海産物との相性は間違いなし」といった声が多く見られ、蔵の目指す方向性が消費者にしっかりと届いていることがうかがえます。福司の酒は、地域の食卓を豊かに彩る名脇役としての役割を果たしているのです。
地域との直接的な繋がり
福司酒造は、地域コミュニティや消費者との直接的なコミュニケーションを大切にしています。
- 蔵元直売所: 酒蔵に併設された直売所(ちょくばいじょ)では、定番商品から季節限定品、蔵元限定酒「霧想雫(むそうしずく)」まで、幅広いラインナップを直接購入できます。かつては酒蔵見学も行われていましたが、現在は休止中です。直売所の営業時間は、平日10:00~16:00、土曜日は10:00~14:00(日曜・祝日は休業)が基本ですが、変更される場合もあるため、訪問前に確認するのが良いでしょう。
- オンラインでの発信: 早くからデジタルプラットフォーム活用にも積極的です。公式オンラインショップを運営するほか、2006年から続く公式ブログ「蔵元ブログ 北のさけくら より」では、製造部長でありオンラインショップ店長も務める梁瀬一真氏らスタッフが、酒造りの様子、新商品の情報、釧路や道東の食文化などを、ほぼ毎日発信し続けています。これは、100年以上の歴史を持つ地方の酒蔵としては特筆すべき取り組みであり、伝統的な流通経路を介さずに消費者と直接繋がり、ブランドストーリーを自ら語ることで、現代の消費者との関係性を築き、ブランドへの親近感とロイヤリティを高める重要な役割を果たしています。ブログは、当初地元での認知度向上を目的に始められた経緯があり、ファンとの対話を生む場ともなっています。
- 地域からの評価の変化: こうした地道な努力と品質向上が実を結び、近年、地元での評価も変化しています。かつては地元以外のお酒を好む傾向もあったそうですが、ここ数年で「福司のお酒、最近どんどん良くなってるね」という声が増え、釧路のお土産として選ばれる機会も増えていると、営業担当者は語ります。これは、福司が単なる地元の酒から、「地元が誇る酒」へと認識されつつあることの表れと言えるでしょう。若手中心の醸造チームが活躍していることも、地域からの関心を集める一因かもしれません。
評価と未来:進化する伝統
福司酒造の酒は、地元釧路のみならず、日本酒愛好家からも着実に評価を高めています。その品質は、日々のレビューや数々の受賞歴によって証明されています。
寄せられる声:味わいの評価
オンラインのレビューサイトや個人のブログなどを見ると、福司の酒に対する評価は概ね肯定的です。「バランスが取れている」「飲みやすい」「食事に合う」といった声が多く、特に「福司 純米酒」は「普通だから飲み続けられる。邪魔せず、主張せず食中酒としての素養が備わっている」と評されるなど、日常的に楽しめる質の高さがうかがえます。季節限定の「しぼりたて生酒」のフレッシュさや、「海底力」のユニークな熟成感など、個別の商品に対する好意的なコメントも目立ちます。もちろん、個人の好みによる評価の差はありますが、「淡麗辛口」でありながら米の旨味も感じられる、という点が共通認識として見受けられます。
輝かしい受賞歴:品質の証明
福司酒造の品質は、客観的な評価によっても裏付けられています。特に権威あるのが、独立行政法人酒類総合研究所が主催する全国新酒鑑評会です。これは、その年に造られた新酒の品質を競う、全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、ここで「金賞」を受賞することは、酒蔵にとって最高の栄誉の一つとされています。福司酒造は、この鑑評会において長年にわたり入賞・金賞を受賞し続けており、北海道を代表する実力蔵として認知されています。
特筆すべきは、近年、原料米を100%北海道産米に切り替えてからも金賞を受賞している点です。これは、かつて最高級とされた兵庫県産山田錦などに頼らずとも、北海道の米と福司酒造の技術によって、全国トップレベルの酒が醸せることを証明する快挙であり、地域への自信と誇りを深めるものです。令和5酒造年度(2023年発表)では金賞を受賞。令和6酒造年度は惜しくも金賞を逃しましたが、令和7酒造年度(2025年春発表)では再び金賞に輝いています。また、札幌国税局が主催する北海道産米を使用した清酒の鑑評会においても、令和7酒造年度に「道産米 吟醸酒の部」で金賞を受賞し、高い技術力を維持していることを示しました(過去13年連続金賞の後、前年は受賞を逃していました)。これらの受賞は、蔵の努力が客観的に評価された証であり、地元の人々や取引先にとっても喜ばしいニュースとなっています。
未来への布石:新しい挑戦
100年を超える歴史を持つ福司酒造ですが、現状維持に甘んじることなく、未来を見据えた挑戦を続けています。
- 新ブランド「五色彩雲」: 近年、「福司」ブランドに加えて、セカンドブランド「五色彩雲(ごしきのくも)」を立ち上げました。これは、「福司」が釧路の地酒として地域の風土を映すのに対し、「五色彩雲」は北海道全体と共に未来へ歩む酒として位置づけられています。この二つのブランドを持つことで、伝統的な「福司」のアイデンティティを守りながら、新しいコンセプトやより実験的なアプローチを「五色彩雲」で展開することが可能になります。これは、市場の変化に対応し、多様な顧客層にアピールするための戦略的なブランド構築と言えるでしょう。
- 継続的な技術革新: 白麹を用いた「COCOROMI」やスパークリング清酒「太陽色のひととき」の開発は、伝統的な日本酒の枠にとらわれず、現代の食文化や嗜好の変化に対応しようとする意欲の表れです。
- 変化への適応: 地域の基幹産業の変化や、昨今の経済状況を踏まえた価格改定など、外部環境の変化にも柔軟に対応しています。
- 次なる100年へ: 福司酒造は、「たかが100年!歴史はこれから動き出す」という気概を持ち、伝統を受け継ぎながらも変化を恐れず進化を続け、次の100年へと繋げていくことを目指しています。
結び:福司に酔う、釧路の未来に乾杯
1世紀以上にわたり、釧路の地で酒を醸し続けてきた福司酒造。その歩みは、幾多の困難を乗り越えてきた不屈の歴史そのものです。冷涼な気候、湿原が磨いた清冽な水、そして北の大地が育んだ米という、釧路ならではのテロワールを最大限に活かし、伝統的な手造りの技と若い感性を融合させた丁寧な酒造り。そして何よりも、地域に深く愛され、釧路の食と文化に寄り添い続ける「地酒」としての姿勢。これらすべてが、福司酒造を唯一無二の存在たらしめています。
「福を司る」という名の通り、福司の酒は、飲む人にささやかな幸福感をもたらしてきました。それは、厳しい自然環境の中で、真摯に酒造りに向き合う蔵人たちの情熱と、地域への深い愛情が溶け込んでいるからかもしれません。
伝統を守りながらも、新しい挑戦を恐れず、常に前進を続ける福司酒造。その一杯には、釧路の過去、現在、そして未来が詰まっています。北の大地の厳しさと豊かさ、そしてそこに生きる人々の温かさを感じさせてくれる福司の酒。ぜひ一度、その味わいに触れ、釧路の魂に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。福司酒造の次なる100年の物語に、心からの期待を込めて。