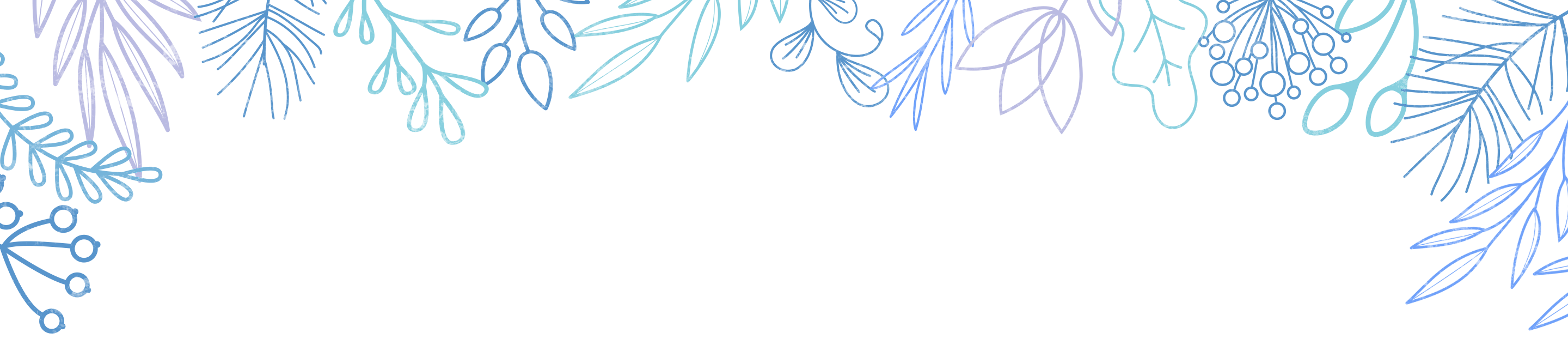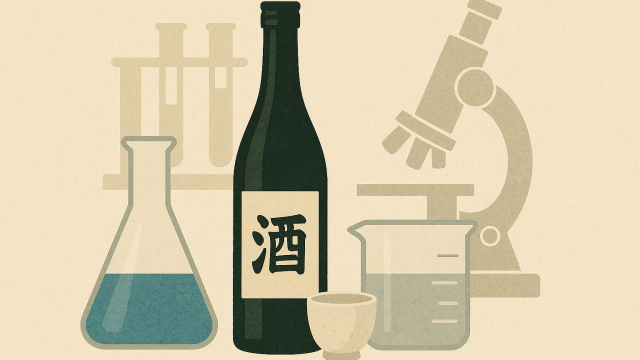函館醸蔵と「郷宝」:道南の土地の味を生かした新しい地酒の誕生
I. はじめに:道南の酒造りに新たな夜明け – 箱館醸蔵の誕生
北海道の南端、道南地域は豊かな食文化、特に新鮮な海の幸で知られているが、長年にわたり地元産の日本酒が存在しない空白期間が続いていた 。約35年もの間、地域の食卓を彩る地酒がなかったこの地に、待望の酒蔵が誕生したことは、地域にとって大きな意味を持つ出来事である 。
その新たな担い手が、函館市の隣、七飯町(ななえちょう)に設立された箱館醸蔵(はこだてじょうぞう)である 。2021年2月に創業したこの酒蔵は、「郷宝(ごっほう)」という名の日本酒を世に送り出している 。その名は「郷(ふるさと)の宝で醸す」という決意を表しており、地域の恵みに対する深い敬意とこだわりが込められている 。箱館醸蔵が掲げる理念は「道南テロワール」。この土地ならではの米、水、そして人の手によって、地域と深く結びついた酒造りを目指している 。
本稿では、この道南の地に新たな息吹をもたらした箱館醸蔵の物語、その酒造りの哲学と技術、主力銘柄である「郷宝」の詳細、そして訪問情報や評価について、深く掘り下げていく。
II. 箱館醸蔵の物語:伝統の復活
A. 醸造への熱意:地元が希求した地酒
箱館醸蔵設立の背景には、道南地域、特に七飯町で100年以上続く老舗酒販店「冨原商店」の女将、冨原節子氏の長年の熱い想いがあった 。豊かな食文化を持つこの地域に、それに合う地元の酒がないことを寂しく感じていた冨原氏は、「いつかこの七飯で日本酒を作り、美味しいお酒をみんなに飲んでほしい」という夢を抱き続けていた 。
その情熱は周囲を動かし、息子たちを中心としたプロジェクトチームが結成される。彼らの目標は、単に酒を造るだけでなく、冨原氏の想いを形にし、道南・函館地域全体に貢献することであった 。地域住民や関係者の間にも、地酒復活への期待は高まっていた。
B. 設立と所在地
多くの人々の支援と努力が実を結び、箱館醸蔵は2021年2月に正式に創業した 。北海道内では14番目、道南地域においては実に約35年ぶりとなる新しい酒蔵の誕生であった 。
酒蔵の所在地は、北海道亀田郡七飯町大中山1丁目2番3号 。JR函館本線の大中山駅の目の前という、アクセスしやすい立地である 。
連絡先は以下の通り。 電話:0138-65-5599 Eメール:office@gohhou.jp
C. 混同注意:箱館醸蔵と函館五稜乃蔵
箱館醸蔵の設立とほぼ同時期に、函館市内にもう一つの酒蔵「函館五稜乃蔵(はこだてごりょうのくら)」が誕生したため、混同されることがあるが、これらは全く別の組織である。
- 箱館醸蔵(Hakodate Jozo):
- 所在地:七飯町大中山
- 主要銘柄:郷宝(Gohhou)
- 設立背景:冨原商店(冨原家)の長年の夢と地域貢献への想い
- 函館五稜乃蔵(Hakodate Goryo no Kura):
- 所在地:函館市亀尾町(旧亀尾小中学校跡地)
- 主要銘柄:五稜(Goryo)
- 設立背景:上川大雪酒造の3番目の蔵として設立(後に独立)、函館工業高等専門学校(函館高専)との連携
- 特記事項:函館市内としては54年ぶりの酒蔵
このように、設立時期が近い二つの酒蔵は、所在地、主要銘柄、設立の経緯や背景において明確な違いがある。
道南地域において、ほぼ同時期に二つの異なる酒蔵が誕生した事実は、単なる偶然以上の意味を持つと考えられる。これは、長らく地酒が存在しなかったこの地域において、日本酒製造への関心と投資が再び高まっていることの現れであり、地域全体の活性化に向けた動きの兆候と捉えることができるだろう。一つの酒蔵の誕生ではなく、地域的なトレンドとして注目すべき現象である。
III. 「郷宝」を醸す:道南テロワールの真髄
A. 哲学:「道南テロワール」の体現
箱館醸蔵の酒造りの根幹をなす哲学は「道南テロワール」である 。これは、道南の米、水、そして人々の手によって、その土地ならではの個性を映し出した酒を醸すという考え方だ。銘柄名「郷宝(ごっほう)」、すなわち「郷(ふるさと)の宝」という名前自体が、この哲学を雄弁に物語っている 。
目指す酒質は「淡麗旨口(たんれいうまくち)」 。単にすっきりとした辛口ではなく、綺麗で滑らかな口当たりの中に、しっかりとした旨味と奥行きを感じさせる味わいを追求している。これは、豊かな海の幸をはじめとする道南の食文化との調和を強く意識した選択である 。
B. 水:横津岳の清冽な恵み (横津岳の伏流水)
酒の品質を大きく左右する仕込み水には、道南の名峰・横津岳(よこつだけ)の伏流水が用いられている 。敷地内の井戸から汲み上げられるこの水は、「中軟水(ちゅうなんすい)」に分類され、酒造りに非常に適した水質を持つ 。
一般的に、軟水で仕込んだ酒はまろやかに、硬水で仕込んだ酒は輪郭のはっきりした味わいになるとされる 。箱館醸蔵が目指す「淡麗旨口」という、綺麗さ(淡麗)と味わいの深さ(旨口)を両立させるスタイルにとって、中硬水や極端な軟水ではなく、「中軟水」を選択したことは、戦略的な判断であった可能性が高い。中軟水は、酵母の活動に必要なミネラルを適度に含みつつ、酒質に過度な硬さや重さを与えず、滑らかさと旨味のバランスを取りやすいと考えられるからだ。
C. 米:北海道の農業遺産
箱館醸蔵は、原料米として北海道産米を100%使用することに徹底的にこだわっている 。使用される米は、北海道における水田発祥の地とされる大野平野(おのおへいや)で、地元の契約農家によって栽培されたものである。
主に用いられる酒造好適米(しゅぞうこうてきまい)は以下の3種類。
- 吟風(ぎんぷう):芳醇な香りと豊かな味わいを生み出すことで知られる 。しっかりとした旨味とコクを持つ酒になる傾向がある 。
- 彗星(すいせい):タンパク質含有量が低く、雑味の少ないすっきりとした淡麗な酒質に向く 。穏やかな香りと味わいで、キレの良い辛口に仕上がることが多い 。郷宝のラインナップでも使用されている 。
- きたしずく:吟風のような大きな心白(しんぱく)と、彗星のような収量性を併せ持つ新しい品種。雑味が少なく、柔らかですっきりとした酒質が期待される 。
さらに、地元七飯町産の食用米であるふっくりんこを使用した純米酒も醸造しており、これは「炊きたての米の香り」と「ふくよかな旨み」が特徴とされるユニークな試みである 。
これらの多様な北海道産米(吟風、彗星、きたしずく)に加え、地元の食用米(ふっくりんこ)まで使用することは、「道南テロワール」というコンセプトへの深いコミットメントを示している。単に「地元の米」を使うだけでなく、それぞれの品種が持つ個性と可能性を探求し、表現しようという意欲の表れと言えるだろう。
また、特筆すべきは**自家精米(じかせいまい)**へのこだわりである 。その年の米の状態を見極め、杜氏自らが精米歩合を微調整することで、目指す酒質をより高いレベルで実現しようとしている。これは品質管理への強い意志と、これらの米のポテンシャルを最大限に引き出そうとする真摯な姿勢の表れである。
D. 技:名匠と最新技術の融合
箱館醸蔵の酒造りを率いるのは、杜氏(とうじ)の**東谷浩樹(ひがしたに ひろき)**氏である 。東谷氏は、北海道での酒造り経験30年以上を誇り、増毛町の国稀酒造(くにまれしゅぞう)で杜氏を務めた経歴を持つ 。全国新酒鑑評会での金賞受賞(通算3度)をはじめ、数々の受賞歴を持つ北海道を代表する名匠である 。函館ラ・サール高校出身という地域への縁もあり、「杜氏人生の集大成をこの蔵で」という強い決意をもって、箱館醸蔵の設立に参加した 。東谷氏は「淡麗旨口」を志向し、「道南テロワール」の具現化に情熱を注いでいる 。
醸造方法としては、**四季醸造(しきじょうぞう)**を採用している 。これは一年を通して酒造りを行う方式で、大手酒造メーカーが生産量を確保するためや、特定の気候条件を利用するために採用することが多い 。箱館醸蔵は比較的新しく、必ずしも大規模ではないが 、四季醸造を取り入れることで、年間を通じた品質管理の徹底、フレッシュな新酒の提供、そして醸造チームの技術向上を効率的に進める狙いがあると考えられる 。
経験豊富な名杜氏を招聘し、自家精米設備を導入し、四季醸造という柔軟な生産体制を整えたことは、箱館醸蔵が設立当初から高い品質基準を目指し、早期に高品質な酒蔵としての地位を確立しようとする強い意志の表れと言えるだろう。これは、新しい酒蔵がしばしば経験するであろう、ゆっくりとした技術習得や品質向上のプロセスを、戦略的に短縮しようとする試みとも考えられる。
IV. 郷宝を味わう:ラインナップの詳細
A. 郷宝のポートフォリオ
「郷宝」ブランドには、純米酒、特別純米酒、純米吟醸酒、純米大吟醸酒といった主要なカテゴリーが存在する 。さらに、使用する酒米(吟風、彗星、きたしずく、ふっくりんこ)や、生酒(なまざけ)、火入れ(ひいれ)、無濾過(むろか)、原酒(げんしゅ)といった製法の違いによるバリエーションも見られる 。また、生酛(きもと)造りの純米酒や、蔵元限定ラベルなども存在する 。
B. 主要銘柄スペック一覧
以下に、調査で確認できた「郷宝」の主要な製品スペックをまとめる。ただし、情報は断片的であり、特に日本酒度や酸度については非公開または情報が見つからない場合が多い点に留意が必要である。価格は特に記載がない限り720mlボトルの税込価格。
| 製品名 (Product Name) | 酒類 (Type) | 使用米 (Rice) | 精米歩合 (Polishing Ratio) | アルコール度 (Alc.) | 日本酒度 (SMV) | 酸度 (Acidity) | 価格 (Price – 720ml) | 特徴・備考 (Notes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷宝 純米 吟風 生酒 | 純米 生酒 | 吟風 (七飯町産) | N/A | N/A | 非公開 | 非公開 | ¥1,540 | – |
| 郷宝 純米 彗星 生酒 | 純米 生酒 | 彗星 (七飯町産) | N/A | N/A | 非公開 | 非公開 | ¥1,540 | – |
| 郷宝 純米 壱火 扁平磨き六割五分 | 純米 火入れ | N/A | 65% (扁平) | N/A | N/A | N/A | ¥1,760 | – |
| 郷宝 純米 別誂 磨き六割 | 純米 | 彗星 (七飯町産) | 60% | 16% | 非公開 | 非公開 | ¥1,870 | フレッシュな酸味と旨味のバランス |
| 郷宝 純米 ふっくりんこ 生酒 | 純米 生酒 | ふっくりんこ (七飯町産) | 65% | 16% | +0.3 | 2.2 | ¥1,870 | 炊きたての米の香り、ふくよかな旨味 |
| 郷宝 特別純米 吟風 | 特別純米 | 吟風 (七飯町産) | 55% | 16% | +4 | N/A | ¥1,980 | マスカット香、旨味と苦味、キレ |
| 郷宝 特別純米 彗星 | 特別純米 | 彗星 (七飯町産) | 55% | 16% | 非公開 | 非公開 | ¥1,980 | 穏やかでフルーティーな香り、すっきりした後味 |
| 郷宝 特別純米 きたしずく | 特別純米 | きたしずく (七飯町産) | 55% | 16% | 非公開 | 非公開 | ¥1,980 | 軽快な味わい、柔らかな旨味、キレ |
| 郷宝 特別純米 吟風 生酒 | 特別純米 生酒 | 吟風 (七飯町産) | 55% | N/A | 非公開 | 非公開 | ¥1,980 | 芳醇な味わいが特徴 |
| 郷宝 特別純米 彗星 生酒 | 特別純米 生酒 | 彗星 (七飯町産) | 55% | 16% | 非公開 | 非公開 | ¥1,980 | 穏やかでフルーティーな香り、すっきりした後味 |
| 郷宝 純米吟醸 壱火 磨き五割 | 純米吟醸 火入れ | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | ¥2,200 | – |
| 郷宝 純米吟醸 彗星 | 純米吟醸 | 彗星 | 50% | 16% | N/A | N/A | ¥2,530 (推定) | 果実香、優しい甘み、すっきりした後味 |
| 郷宝 純米吟醸 きたしずく | 純米吟醸 | きたしずく | 45% | 16% | 非公開 | 非公開 | ¥2,420 | 柔らかな旨味と余韻、キレ |
| 郷宝 純米吟醸 別誂 磨き四割五分 | 純米吟醸 | きたしずく | 45% | 16% | 非公開 | 非公開 | ¥2,420 | 柔らかな旨味と余韻、キレ |
| 郷宝 純米大吟醸 壱火 磨き四割五分 | 純米大吟醸 火入れ | N/A | 45% | N/A | N/A | N/A | ¥2,640 | – |
| R6BY 郷宝 純米大吟醸 壱火 磨き三割五分 | 純米大吟醸 火入れ | N/A | 35% | N/A | N/A | N/A | ¥3,300 | – |
| R6BY 郷宝 純米大吟醸 別誂 磨き二割五分 | 純米大吟醸 | N/A | 25% | N/A | N/A | N/A | ¥5,500 | – |
| 郷宝 生酛純米 壱火 | 生酛純米 火入れ | 吟風 | 65% | 16% | +7.5 | N/A | ¥1,870 | 穏やかな香りと熟成感、キレ |
| 郷宝 試 純米 無濾過生原酒 北冴60% | 純米 無濾過生原酒 | 北冴 | 60% | 18% | +4 | 1.7 | ¥2,420 | 試験醸造、フレッシュ感 |
| 郷宝 試 純米 壱火原酒 北冴60% | 純米 火入れ原酒 | 北冴 | 60% | 18% | +4 | 1.7 | ¥2,420 | 試験醸造 |
注:スペック情報は複数の出典から統合しており、一部矛盾や欠落がある可能性があります。最新情報は公式情報をご確認ください。BYは醸造年度 (Brewery Year) を示します。R6BYは令和6醸造年度(2024年7月~2025年6月頃)。
C. 香りと味わいの特徴
「郷宝」の味わいは、その目指す「淡麗旨口」というスタイルを反映している 。全体的に、綺麗で滑らかな口当たりでありながら、米由来のしっかりとした旨味と、穏やかながらも存在する酸味がバランス良く感じられるのが特徴である。
香りは、派手さはないものの、穏やかで心地よいものが多い。銘柄によってはマスカット や果実のような香り 、あるいは炊き立ての米を思わせる香り が感じられる。
味わいは、使用する酒米によってニュアンスが異なる。「吟風」を使ったものは、ふくよかで力強い旨味が特徴的であり 、「彗星」を使ったものは、よりすっきりと軽快で、キレの良い爽やかな味わいとなる傾向がある 。「きたしずく」は、柔らかな旨味とキレの良さを併せ持つ 。後味は総じてキレが良く(キレ)、飲み飽きしない食中酒としての性格が強い 。一部の銘柄やレビューでは、後味に心地よい苦味(苦味)が感じられることもある。
D. おすすめの飲み方と料理との相性
「郷宝」は、その「淡麗旨口」な特性から、幅広い温度帯で楽しむことができる。純米吟醸や純米大吟醸は、冷酒(5~15℃程度)でその華やかな香りや繊細な味わいを引き立てるのが良いだろう 。一方、特別純米酒や純米酒は、冷酒から常温、さらにはぬる燗(40℃前後)まで、温度帯によって変化する旨味やキレを楽しむことができる 。
料理とのペアリングにおいては、特に道南・函館の豊かな海の幸との相性が抜群であると、多くの情報源で強調されている 。
- 刺身:イカやマグロなど、素材の味を活かした刺身と合わせることで、郷宝の持つ米の旨味と魚介の繊細な味わいが互いを引き立てる 。
- 焼き魚:ブリの照り焼きのような、やや味付けのしっかりした焼き魚とも相性が良い 。郷宝の持つ旨味とキレが、魚の脂やタレの風味と調和する。
- 牡蠣:濃厚な旨味を持つ牡蠣(生牡蠣、焼き牡蠣など)とも好相性 。郷宝の持つ酸味やキレが、牡蠣の風味を引き締め、後味をすっきりとさせる。
- その他魚介料理:浜焼きや、アンチョビを使ったパスタ、ピザなど、様々な魚介料理と合わせやすい 。
このように、郷宝が地元の魚介類と特に推奨されている点は、「道南テロワール」というコンセプトが、単に原料だけでなく、地域の食文化全体との繋がりを重視していることの表れである。郷宝は、道南の食卓を豊かに彩る、まさに「郷の宝」としての役割を担っていると言えるだろう。
V. その他の製品と蔵元訪問
A. 「郷宝」以外の製品について
ユーザーの問い合わせにあった「函館奉行」という銘柄について調査したところ、これは箱館醸蔵の製品ではないことが判明した 。この銘柄は、函館産の酒米「吟風」を使用しているものの、醸造は兵庫県伊丹市にある小西酒造が行っている 。函館との関連はあるが、箱館醸蔵のラインナップとは異なるため注意が必要である。
箱館醸蔵がリキュールなどを製造しているかについては、現時点での情報は見当たらなかった。
B. 箱館醸蔵への訪問
箱館醸蔵では、酒造りの様子を見学したり、製品を試飲・購入したりすることが可能である。
- 見学・試飲:
- 専門的なガイド付きツアーの有無は不明だが、醸造施設の一部をガラス越しに見学できるスペースが設けられている 。
- 併設の直売所では、無料で郷宝の試飲が可能である 。
- 蔵元直売所:
- 酒蔵に併設されており、郷宝の各銘柄や、蔵元限定ラベルの製品も購入できる 。
- 営業時間:土曜日、日曜日、祝日のみの営業。時間は午前10時~12時と午後1時~4時の二部制 。平日は営業していない点に注意が必要である。
- アクセス:
- JR函館本線「大中山駅」の目の前 。
直売所が週末と祝日のみの限定的な営業となっている点は、注目に値する。これは、比較的新しい、あるいは小規模な酒蔵の運営体制を反映している可能性もあるが、同時に、平日の広範な小売活動よりも、週末に訪れる観光客や地元住民との直接的な交流や体験提供を重視する戦略の表れとも考えられる。
VI. 評価と評判
A. 受賞歴と評価
箱館醸蔵は比較的新しい酒蔵であるが、その品質は早くも評価されている。
- 北のハイグレード食品:「郷宝 特別純米酒」が令和4年度(2023年発表)の「北のハイグレード食品」に選定された 。これは、北海道が食の専門家と共に選定するものであり、道産食品の中でも特に優れた品質と認められた証である。
- 杜氏の実績:杜氏である東谷浩樹氏は、前職の国稀酒造時代を含め、全国新酒鑑評会で通算3度の金賞を受賞するなど、豊富な経験と確かな技術を持っている 。この名匠の存在が、郷宝の品質の高さを支える大きな要因となっている。
- その他の受賞歴:現時点では、「北のハイグレード食品」以外に「郷宝」または「箱館醸蔵」としての具体的な受賞歴は確認されていない 。
B. 消費者の声と市場での評判
レビューサイトやブログなどでの評価を見ると、「郷宝」は概ね好意的に受け止められている 。特に、目指す「淡麗旨口」の通り、旨味と酸味のバランスの良さ、後味のキレ、そして食事(特に海産物)との相性の良さが評価されている点が多い。
ただし、箱館醸蔵は設立から日が浅いため、全国的な知名度や長期的な評価はこれから形成されていく段階にある。しかし、経験豊富な杜氏の招聘、品質への明確なこだわり、そして「北のハイグレード食品」選定という早期の地域的評価は、今後の発展を期待させるものである。現在のところ、流通が道南地域や一部専門店に限られている可能性があり 、これが広範な評価を得る上での制約となっているかもしれないが、品質本位の姿勢は着実に評価され始めていると言えるだろう。
VII. 結論:道南の酒の未来
箱館醸蔵の誕生は、長らく地酒不在であった道南地域にとって、まさに待望久しい出来事であった。単に酒を造るだけでなく、「道南テロワール」という明確なコンセプトを掲げ、地域の米、水、そして人々の情熱を結集して「郷宝」という名の酒を生み出したことは、地域文化の復興と活性化に大きく貢献するものである。
名匠・東谷浩樹杜氏の技と、横津岳の伏流水、そして吟風、彗星、きたしずくといった個性豊かな道産米が織りなす「淡麗旨口」の味わいは、道南の豊かな食、とりわけ新鮮な海の幸との相性を追求して設計されている。その土地の食文化に寄り添う姿勢は、郷宝が真の「地酒」たる所以であろう。
比較的新しい酒蔵でありながら、品質へのこだわりは徹底しており、「北のハイグレード食品」への選定はその証左である。四季醸造の採用や自家精米といった取り組みも、品質向上への飽くなき探求心を示している。
函館・道南を訪れる機会があれば、ぜひ箱館醸蔵に立ち寄り、その土地の空気と共に「郷宝」を味わってみることをお勧めしたい。また、道南の海産物と共にこの酒を嗜むことは、まさに「道南テロワール」を五感で体験する最良の方法であろう。箱館醸蔵と「郷宝」は、北海道の日本酒シーンに新たな彩りを加え、道南の酒文化の未来を明るく照らす存在となるに違いない。この「郷の宝」が、今後どのように磨かれ、輝きを増していくのか、大いに期待したい。